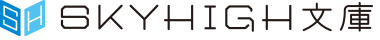21グラムの恋 立ち読み
「ちょっとナッツってば、早く!」
「待ってよ、浅海!」
急かす親友の声に、凪月は窓の外に向かって鞄を放り投げた。きらりと光る太陽が眩しい。グラウンドから立ち上るむっとする熱気に顔をしかめながら、窓の外を覗いた。
宮下凪月、十七歳。県立夕ヶ浜高等学校二年。
親友の榎田浅海は、凪月を〈ナッツ〉と呼ぶ。入学式で出会ってからずっとこの愛称だ。
そんな凪月は、浅海と二人、目下脱走実行中である。
窓枠に足をかけると、グレーのチェックのプリーツスカートは、きわどいところまでめくれてしまっていたが、気にしちゃいられない。
足踏みをしながら凪月を待っていた浅海の耳に、二時間目の始業のチャイムがタイムリミットを知らせた。
「やばいよ、ナッツ」
「わかってるっ」
夕ヶ浜高校の校舎はL字型に建っている。
正門から入ると、一階に職員室、二階からは各教科ごとの教室などがある東側校舎。堂々と正門から抜け出すバカはいないだろうが、教師の目を逃れての脱走はまず不可能だ。一方の南側グラウンドに面した北側校舎も、斜辺上に位置する職員室からは丸見え状態である。
ならばと、凪月と浅海は職員室から一番遠い北側校舎にある美術室から抜け出そうとしていた。運が良ければ、ここが脱走ルートの最短距離になる。
「ほらっ」
「サンキュ」
浅海の手を借りて地面に降り立った凪月は、慌てて鞄を拾い上げると猛ダッシュした。耳の後ろで二つに結わえた髪が跳ねる。
「こらーっ! そこの二人ーっ! どこに行くんだーっ! 待ちなさーいっ!」
職員室の窓から、怒りの声が響き渡った。
学年主任、鬼瓦の声だ。もちろん鬼瓦というのはあだ名で、日本家屋の屋根の上で睨みを利かせている鬼の面容に似ているからだ。
待てと言われて待つわけないし、と凪月は胸中で毒づいた。
校舎中からガタガタと椅子の音が聞こえ、物見高な生徒たちが顔を出す。
「おまえたち、席に着けっ」
あちこちの教室から聞こえてくる怒鳴り声と笑い声をあとに、体育館裏を抜けて自転車置き場へと走る。ここに一部分だけフェンスの壊れたところがある。巧妙に隠されているあたり、二人より先に脱走を企てた猛者がいるのだろう。
どちらからともなく笑い出した。
走りながら笑っているので、バス停に着く頃には息も絶え絶えになっていた。
「はー、おかしい」
浅海は横っ腹を押さえながら笑っている。肩で切り揃えられた栗色の髪は、陽射しに透けて輝いていた。浅海はやや童顔な凪月に比べると美人系だと思う。でも取り澄ましたところは皆無だし、優しくて頼りがいもある。凪月はそんな浅海が自慢だったし、大好きだ。
「鬼瓦、もう二時間目始まってたのに容赦ないねー」
凪月も目尻に溜まった涙を拭った。
「迷惑じゃんね」
「けど、その原因ってあたしらだから」
二人で顔を見合わせると、またケラケラと笑った。
潮を含んだ風が、凪月のおくれ毛をさらっていく。
真っ直ぐな国道を、ブルーのバスがやってきた。車体の脇にはカモメをイメージしたという白いラインが入っている市内循環のバスだ。
「あ、来たよ」
凪月は逆光に目を細めた。
平日のバスは空いている。二人は後部座席の二人掛けシートに並んで座った。
窓の外には見慣れた海が広がっている。夏の間、海水浴客で賑わっていた海岸にも人影はなく、日一日と深まる秋の空との境界も曖昧になっていた。
バスはしばらく海岸線を走ると、市街地へと入って行く。
やがて大きな体育館が見えてきた。目指すのは体育館隣にある武道館……の隣に併設されている弓道場だ。
降車ドアが開ききるのを待たずに、凪月は飛び出した。
「行くよ、浅海」
「あっ、待って!」
〈関東選抜弓道大会男子の部〉と掲げられた入り口を抜けると、さながら武家屋敷のような佇まいを見せる弓道場がある。
二人は、ぶ厚いアクリル板で仕切られた観覧席の端に陣取った。階段状のコンクリートに座席が設けられただけの席に座ると、凪月は深く息を吸い込んだ。
微かなざわめきの中にも、ピンと張りつめた空気が心地いい。
いた─―。
今まさに弓を引こうとする人物がいる。
逢坂秋之。三年、弓道部主将。
射場には三人いて、こちら側から見れば一番手前に立つその人。
涼やかな横顔。引き結んだ唇。後ろへと流した前髪の一束が、聡明そうな額にかかっていた。
無駄な力のない構えで弓が頭上に掲げられ、ゆっくりと弦が引かれていく。凪月は息を止めて両手を握りしめた。
離れた!
矢は真っ直ぐに弓を離れ、空を裂きながら、飛んでいく。タンッ、と小気味好い音を立てて、矢は的に中った。
観客席の部員たちから「よし!」と声がかかる中、凪月は「やったあ」と浅海と手を握り合って喜びの声をあげた。マネージャーの咎めるような視線が向けられたが気にしない。凪月はペロッと舌先を出して肩をすくめた。
何てきれいなんだろう。
うっとりとした眼差しを向けた先には、弓道衣を纏う、凛とした秋之がいる。見ているだけで心拍数が上がり、頬に熱が灯る。部員でもない限り、平日に開催される試合を見ることなど不可能だ。これなら授業をサボった甲斐があるというもの。あとで叱られるのなんて覚悟の上だ。
秋之は、周りのざわめきも、突き刺さるような審判の目も意識していない。粛々と競技を続け、一人、また一人と脱落していくプレッシャーをも易々と跳ね除けていた。
秋之の素晴らしさは、正射正中……心身共に正しく射れば正しく中る……の技術もさることながら、神棚に向かって拝礼するところから、退場するその時までの所作が素晴らしく美しいところだ。
それに比べて……と凪月の溜息を誘ったのは、秋之の一つ後にいる斉藤翔だ。三軒隣の家に住む、凪月の幼なじみである。
弓道の腕は認める。的中制で行われる個人競技で、我が校ですでに残っているのは秋之と翔だけだ。
完璧な武道と言わしめる秋之に対して、翔の弓は中ればラッキーとでも思っているような、半ば運任せのようなところがある。すべてにおいて大雑把なのは、翔の性格によるところが大きい。
「あっ」
翔の放った矢がわずかに逸れた。一射外してしまった。それでも四射中、三射的中。予選通過だ。これで秋之も翔も、二次予選に進むことになる。
翔の口がひん曲がった。今にも地団駄を踏みそうな表情に、凪月は吹きだした。
矢が離れた後も、的を見据えたまま平静を保つ残心まで重要とされているのを、よもや忘れているんじゃないだろうかと思う。
バーカ、と内心舌を出していると、隅に控えていたマネージャーが睨みつけてきた。
「おお、こわっ」と、浅海は両腕を抱いて、大袈裟にぶるっと震えてみせた。
「マネージャーの西野さんね、翔くんのことが好きなのよ」
「は?」
浅海の言葉に、凪月は思わず訊き返した。
「一年の時に翔くんに一目惚れしたんだって」
気をつけなさいよーと言いながら、浅海は凪月の肩を押した。
「あの人、ナッツを目の敵にしてるんだから」
「敵って……」
「好きな男が四六時中他の女とべったりしてるんだもん。そりゃあ面白くないでしょう」
「別に四六時中なんて。ってか、うざいのはあいつの方だし」
口を尖らせた凪月は、今の今までマネージャーの名前さえ知らなかったことに気づいた。
制服のタイの色が赤なので、同じ二年なのは知っている。夕ヶ浜高校では学年をタイの色で区別している。一年は緑、二年は赤、そして三年は青だ。
だけど、睨まれたって困る。
何の因果か翔とは同じクラスだし、席だってくじ引きで凪月の斜め後ろなのだ。そんなこと、凪月にとっては不可抗力だ。
「てか、浅海も知ってるくせに!」
「あー、はいはい。ナッツは王子様ひとすじだもんねー」
女子の間で夕ヶ浜の王子様と言えば秋之のことだ。
成績優秀でスポーツ万能。すらりとした高身長に整った容姿。天は二物も三物も与えるのだと、誰もが憧れとわずかな妬みを抱いて、そう思う。
凪月もその例に漏れない。視線の先の王子様に密かな恋心を抱いて二年になる。新入生歓迎会のイベントで、彼が弓を引く姿を見てからというもの、凪月の目は秋之に釘づけなのだ。
そういえば、と凪月は思い出した。新入生歓迎会の翌日のことだった。
「俺、弓道部に入ったから!」
鼻息荒く宣言した翔に、凪月は目をぱちくりとさせた。
「はい?」
「だーかーら! 弓道部に入ったっつってんの!」
「……誰が?」
「おまえなあ……」
あの時は散々笑っちゃったけど、弓道部に入部した翔は本気だったんだ。今でもあの時のことを思い返すと、悪いことをしたなあ、と反省している。
今度チーズバーガーでも奢ってやるか。
いささか上から目線で凪月が気持ちをリセットすると、ふと、誰かの視線を感じた。
観客席をぐるりと見回す。座っているのは、ほとんどが弓道部の学生だ。他には引率の教員に近所のおじさんたちばかりだけど……。
あ。いた。うわあ、きれいな人。
凪月はその人に視線を定めた。観客席のほぼ中央に座っている。間違いない。あの人だ。
九月とはいえ、まだまだ日中は暑い。なのに、その人ときたら全身黒ずくめだった。薄手の黒いロングコートに黒いシャツ。黒いボトムに黒いエンジニアブーツ。本当に真っ黒だ。
凪月が確信すると同時に、視線が交差した。その人は驚いたように目を見開くと、次の瞬間にはふわりと微笑みを浮かべた。
知っている人だろうか……とフルスピードで記憶を探りながら、とりあえず小さく頭を下げる。すると向こうも、より笑みを深くしながら同じように頭を下げてきた。
正直、ちょっとドキドキしていた。
歳の頃は二十代前半くらいだろうか。すっきりとした目鼻立ちの涼しげな容貌。驚くほどの美形なのに、なぜか親しみを感じるのは、ゆるりと細められた目と、優しく笑みを浮かべている口元のせいかも知れない。
「浅海」
凪月は浅海のニットベストの裾を引っ張った。
「ねえ、見て。すごいイケメン」
「逢坂先輩のイケメンっぷりは誰でも認めてるって」
「違うよっ。ほら、あそこ」
耳にタコ、といった表情の浅海の腕を、ぐいっと引き寄せた凪月だったが「あれ?」と首を傾げた。
もう一度観客席を見渡したが、青年の姿はどこにも見当たらない。
「どこよ」
「いない……」
消えた。
「さっきまであそこに座ってたんだよ」と言う凪月に「イケメンなら、あたしも見たかったなあ」と八割方本気にしていない浅海が、両手を上げて大きく伸びをした。
「ナッツ、どうする? 学校に戻る?」
大会個人戦の部は無事に終わり、射場にはすでに団体戦に参加する生徒が並び始めている。
「んー。お昼食べてからでも良くない?」
二人は顔を見合わせるとにんまりと笑った。
観客席から外へ出た凪月は、再び周囲に視線を巡らせた。
観客席の出入り口は両側に一つずつあるが、九十人収容の真ん中の席からは遠い。あの黒ずくめの男の人、いつの間に出ていったんだろう。
首を傾げていると、ポカッと後頭部を叩かれた。