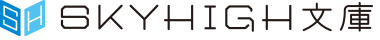零の記憶 瞬く星と見えない絆 立ち読み
窓から見えるソメイヨシノが、ちらり、ちらり、と最後の名残を散らしている。
例年より肌寒い気候に、遅ればせながら咲いた桜もすっかり葉桜に変わる頃。
都立清涼高校2年D組を担任する鈴宮一貴は、放課後の解放感に浮わついた生徒達の合間を縫って職員室を目指していた。
前年度から少しずつ進められていた校内の改修工事が竣工を迎えたため、いくつかの教室はこの春から新しい配置となっている。
職員室と学年教室は、今までH形の校舎の渡り廊下を挟んで左右に分かれていたのだが、防犯上とか教育上とかの理由で同じ建物内に収まることになった。
しかしながら染み付いた習慣はなかなか抜けきらないもので、新学期も始まってしばらく経つというのに、うっかり渡り廊下を渡ってしまう教師は一人や二人ではなかった。
「あー……しまった」
例に漏れず一貴もその一人で、職員室に戻ってからの仕事の手順を考えているうちに、いつの間にか渡り廊下を半分ほど渡ってしまっていた。
「面倒だなあ、これ」
頭を掻いて方向転換をする。
頭を掻くのはバツが悪い時。戸惑い、気恥ずかしさを宥める行為。
自分の仕草が示す心理が頭をよぎって、一貴は思わず苦笑した。
数ヶ月前に関わったある事件をきっかけに、昔習得した心理学をまざまざと思い出したせいで、今でも時折こうしてデータとしての情報が記憶の底から蘇る。そうかと思うと一番知りたい相手の心情はうまく推し量れないのだから、難儀なことだ。
やれやれと肩を竦めて渡り廊下を戻ると、突き当たりで何やら小さな悲鳴が上がった。
「うわ」
どか、と横腹に衝撃を受けて一瞬よろめく。何事かと視線を落とした先で見慣れた金髪が広がるのを見て、一貴はとっさにそれを抱き留めた。
「え、如月?」
片腕にすっかり収まる小柄な体躯に、生まれたてのヒヨコのような色の髪。制服を着崩し、指定されたものではない男物のタイを緩く締めたその女生徒は、件の事件で関わりを持つようになった、如月零であった。
「──」
ぶつかった衝撃に身を縮めていた零が、腕の中で何か言う。
「なに?」
聞き取れなくて覗き込むと、零が右腕で庇うように顔を隠した。次いで左腕をめいっぱい突っ張って、一貴の体を遠ざける。
「……さわ、んなっ!」
腕の下から覗く透明感のある白い肌がみるみる赤く染まっていく。
何にぶつかったのか、誰の腕に抱き留められたのか、理解しての反応らしい。
「お前さー……」
一時はずいぶん距離を縮めたようにも思えたが……相変わらず免疫無いというか慣れないというか。
どこか残念な思いを胸に、一貴はちょっと苦笑した。
気配を察した零が、増々赤くなって怒ったように後ずさる。
「待て、待て。危ないから」
顔を隠したままの右腕を掴んで引き止めると、零の肩が、びく、と小さく跳ねた。
「あれ、お前」
ふと、あることに気がついて、一貴は辺りを見回した。
ぶつかった時に落としたのか、彼女のトレードマークとも言えるやや大振りの黒縁眼鏡が無くなっている。
だから執拗に顔を隠すのか。合点がいって、一貴はため息をついた。
零は裸眼では何も見えない。いや、見え過ぎる。
視界を守るはずの眼鏡を失ってなお、「困った」とも「拾って」とも言わない不器用な子どもに歯がゆさを感じながら、一貴は足下で踏み潰される危機に瀕していた眼鏡を見つけると、それを拾い上げた。
「ほら」
捕まえていた腕を離して手の中に眼鏡を押し込んでやると、零がはっとしたように息を呑んだ。
何事か言いかけて、唇を噛む。言えない言葉を飲み込む時、彼女は唇を噛むのだ。
結局何も言わぬまま手探りで眼鏡をかけると、零はそっと確かめるように目を開いた。
シャンパントパーズに似た大きな薄茶色の瞳が世界をゆっくりと捉えていく。
神聖な儀式を目撃するようなこの瞬間に、一貴はもう何度も立ち会っていた。
「それで、どうしたんだ。そんなに慌てて」
零にぶつかるのはこれで二度目だ。
普段何事にも興味を示さない零が、小走りとはいえ走るほど慌てるなど、そうあることではない。
前にぶつかったのは親友の訃報に驚いた零が教室を飛び出した時だった。
今度は何だ。
訝る一貴の視線から逃れて、零がぷい、と横を向いた。
「別に。何でも無い」
関係ないだろ、と突き放す。変なところで意地を張るのは出会った頃から変わらない。
「何でも無いって、お前な」
前方不注意でぶつかっておいて、何が「別に」か。
見え透いた誤魔化しに呆れていると、どこからともなく軽快な足音が近づいて来た。
「あっ、いたいた! 零ちゃーん」
駆け寄ってくるのは、この春クラス替えで零と同じ2年D組になった男子生徒、水嶋遙だ。つまり零と遙は、一貴の担任するクラスの生徒ということになる。
遙の声を耳にした途端、零がぎくりと顔を強ばらせた。
──なるほどこいつが原因か。
零が何から逃げて来たのかを察して、一貴は肩を竦めた。
「探しちゃったよ零ちゃん! 今日こそ来てよ、ワンゲル部!」
屈託の無い笑顔で迫る遙に、気圧された様子で零が一歩後ずさる。
ここのところしつこく零に絡んでいく遙は、どうやらどこの部にも属していない零を自分の部に引き入れたいらしい。
色々あって他人と没交渉気味の零は、そんな遙をどうあしらっていいか分からないようで、結果逃げ回ってはこれを避けていた。
「ねえ、先生。先生からも言ってよ、零ちゃんに。山登りは楽しいぞーって。あと、水嶋くんと一緒にいると楽しいぞ! って」
懇願する遙は並ぶと一貴より少し背が高い。よく動く表情が特徴的で、言い換えれば顔から全てがだだ漏れだ。やや明るいマットブラウンの髪はゆるく波打ち、左右の耳にはピアス穴が空いていて、時々、外し忘れたらしい小さな石が残っていた。
「俺に何か頼むつもりなら、まずは毎朝遅刻せずに登校してからにしろ」
「どき」
さりげなく零を背中に回して軽く去なすと、妙な効果音を口にして、遙がさっと身構えた。叱られる前の警戒ポーズだ。
「お前なあ。前年度の担任は留年阻止のために毎朝モーニングコールしたらしいけどな。俺はやらないぞ、そんな面倒なこと」
「うう。だって、しょうがないじゃん。起きられないんだもん」
「だから起きろよ。あと提出物。あんまり溜めると成績から引かれるぞ」
「ぐぬぬ。それ今言うことー……?」
「今言わなくていつ言うんだ。ちなみに俺の教科ではもう減点対象にしたから。後はテストで挽回しろ」
「うぎゃあ! なんてことだ! 警告無しか! 鬼だよ鬼! ……て、ちがーう! ああもうそれはそれ! 俺は今、零ちゃんを誘ってるの!」
ぎゃんぎゃん騒いで、遙が話を元に戻す。
一貴の後ろで空気になっていた零が、ぴし、と緊張する気配がした。
それにしても。
「水嶋お前、…何でそんなに如月に拘んの」
どこに行っても可愛がられ、受け入れられる遙はクラスを超えて友人も多い。ほとんど常に誰かがそばにいる。それなのに、わざわざその輪を振り切って零に近づくのだから、理由を尋ねたくもなる。
え、と目を丸くして、遙が一貴を凝視した。
「仲良くなりたいのに理由とかいるの?」
まばゆいばかりに澄んだ瞳で問い返されて、一貴は思わずたじろいだ。
たじろぎついでに、背後の零に囁く。
「──お前もう、水嶋と仲良くしてやったら?」
「無茶言うな!」
こちらも囁き声で返して、零が必死に一貴を睨んだ。
人を遠ざけて、日々を無難にやり過ごしていた零にとって、ぐいぐいと遠慮なく踏み込んで来ようとする遙のようなタイプは苦手なのかもしれなかった。
「うーん」
難しい顔で唸る遙が、懸命に一貴の問いに答えようと言葉を探す。
「えっとー……零ちゃん可愛いし、なんか反応面白いし……それからー……そうだ! 知ってる? 零ちゃんの弟と俺の弟、同じ中学校なの」
「え」
これには零が反応した。
両親の再婚を機に姉弟になった晃を、零は特別気にかけている。
「びっくりした?」
零から反応を引き出せたことが嬉しいようで、遙が満面の笑みを浮かべた。
「しかも同じ学年なんだよー。クラスは違うみたいだけど、俺時々晃くんの話聞くんだ。弟同士仲良いんだから、俺達も仲良くなろう!」
にこにことよく分からない理屈を繰り出す遙を、零が一貴の後ろから恐る恐る、しかしはっきりと興味の眼差しで覗いている。
「うまく釣ったなあ、水嶋」
感嘆すると、「何が?」と首を傾げるのでどうやら無自覚らしいが、一貴が知る限り、二人は今、初めて視線を交わしていた。
「よかったな如月。友達できそうで」
「!?」
一貴の言葉にがばっと顔を上げると、零が無理無理! と首を振る。
一方遙は目を輝かせて、ぐい、と距離を詰めると、零に顔を近づけた。
「そうだよ零ちゃん、友達になろう! そんで一緒に山に登ろう! 山はいいよ! 楽しいよ!」
「ひ」
驚いた零が猫のように飛び上がって、反射的に一貴の背中にしがみつく。
そこに他意が無いことを知りつつも、真っ先に縋る相手が自分であることにささやかな愉悦感を抱いて、一貴は込み上げる感情を苦労して嚥下しなければならなかった。
「えっ。何で隠れるの? 零ちゃーん」
「水嶋。水嶋離れろ。顔を寄せるな。お前どうしてそんなにパーソナルスペース狭いの? ちょっとは加減してやりなさいよ。如月が怯えるだろ」
「でも先生はもっと近いじゃん」
無邪気な遙の指摘に、一貴の体が怯んで傾く。
お前、それをここで言うか。
恨めしそうに遙を睨んだのは、そこを突いてしまったら、背中の子どもが後悔に苛まれるに違いないからだ。
案の定、ぱっと一貴の背後から零の気配が消えて、人知れず一貴は落胆した。
ほんの一瞬、息の詰まるような空気が一同を包み込む。
そこへ。
「見つけたわよ、水嶋くん」
溌剌とした声が投げ込まれて、新たな人物がこちらへ近づいて来た。
異動によって今年度から清涼高校勤務となった女性教員、相良志帆だ。
肩先に触れる長さの黒髪に、黒目がちの瞳。若い歳を更に若く見せる童顔と女性らしい濃やかさで、相良は着任早々、男子生徒を中心に生徒達の心を掴んでいた。
「あなたね。提出してない課題、いい加減出しなさいよ。遅刻数を特別課題でなあなあにしてあげようっていう私の親切心を少しは汲み取って」
困ったように眉尻を下げて笑う、相良の担当科目は英語だ。D組の場合、英語は一限に入っている曜日が多く、つまり遙の遅刻の煽りを一番に食っている。
「あっ志帆ちゃん! いい所に」
反省する素振りなど1ミリも見せずに、遙が相良を笑顔で迎えた。
「今ね、零ちゃんをワンゲル部に誘っててね。志帆ちゃん顧問でしょ、協力してぇ」
相良の説教など意にも介さずおねだりする遙は、腹が据わっているのかただのアホなのか。
諦観していると、扱いに慣れている様子の相良がちょっと首を竦めてから、零を見やった。
「如月さんは、山登り好きなの?」
水を向けられた零が、戸惑うような表情を浮かべる。
「特には……」
「えっ? 何で? 山嫌い? 高い所だめ? それとも運動が嫌?」
「こらこら水嶋くん」
矢継ぎ早に質問を繰り出す遙をたしなめて、相良が柔和に微笑んだ。
「無理強いしても好きにはならないわよ」
そうねえ、と思案しながら相良が指先を顎に当てて遠くを見つめる。
「そうだ如月さん。良かったら試しに今度のナイトハイクに参加してみない? うちの部活、所属部員は規定数を満たしてることになってるけど、実際は水嶋くんくらいしか活動に出て来ないから、これは民間の企画に参加する形のものなんだけどね。尾山っていう標高約580メートルの低い山を夜に登るのよ。ちょうど春の流星群のピーク時で、目的は登山より天体観測の方にあるから登りやすいコースを行くの。登山慣れしていなくても大丈夫よ」
「流れ星」
繰り返した零の大きな瞳に、ちらりと好奇の色がよぎる。