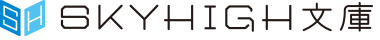神様、縁の売買はじめました。 立ち読み
一〇月一週目の月曜日である。
月が白くくっきりと輝く、晴れた秋の夜だった。
陽が暮れると気温が急に下がる季節になり、学校では本日、衣替えが実施された。制服のブレザー姿で、ほどよく涼しい夜道を、信也はぶらぶらと散歩気分で歩いていく。
ぽつぽつと街灯の灯る閑静な住宅街を進み、ベンチと砂場と太い桜の木が一本あるだけの小さな公園を近道に突っ切ると、よく利用するコンビニの看板が見えてきた。
このコンビニの狭い駐車場には、不良連中がバイクを停めて溜まっていることがある。そういうときは関わり合いにならないよう軽く迂回して自動ドアを目指すのだが、運よく今日はいかついお兄さん方はいなかった。
しかし代わりに、焼き鳥を頬張る女性が一人、建物の壁にもたれながら立っていた。
不良相手なら視線を落としておずおず通行する信也だが、その女性には逆に目を奪われてしまった。
彼女は薄いピンクの小紋の着物を身につけていた。そこにパッと見では無地に見えてしまうほど細かな柄つけがなされた若草色の帯に、帯と同色の草履。都会とも田舎とも言いきれないごく普通の住宅街の真ん中で、その着物姿はかなり浮いていた。
加えて、彼女はすごく美人だった。歳は二〇代後半くらいか。女優をやっていると言われても疑わないだろう、美しく整った顔。腰まである艶やかな白金色の髪は、毛先が赤い紐で結わえられていて、周囲の明かりを浴びて光の粒子を纏ったように輝いている。
はんなり清楚な装いをした女の人が……コンビニの壁にもたれて焼き鳥。しかもよくよく見れば地面に口の開いた缶ビールまで置いているものだから、ミスマッチ感が半端ない。目を惹きつけられつつも、信也は直感的にこう思った。
この人……もしかしたら不良よりも目を合わせちゃいけない類の人なんじゃ……。
結局、着物の女性に関してはそれ以上気にしないことにして、信也は下を向きながらコンビニに入店した。
それから二〇分ほど、信也は目当ての漫画週刊誌をパラパラと立ち読みした。読み終わった冊子を棚に戻すと、いつものように夜のネットゲームに備えてジュースとスナック菓子を買う。
「あざっしたー」
毎度おなじみの店員のやる気のない声を背中に聞きながら、信也は店を出た。そして。
「………………」
ちらり、と。やはり建物の壁の方を窺い見てしまった。
例のお姉さんはまだそこにいらっしゃった。
しかもそのポーズはさっきよりもひどい。壁にもたれながらしゃがみこみ、缶ビールを呷っている。はだけた着物の裾のその奥が見えそうで、思わず信也は二度見しそうになり、慌てて目を逸らした。
いかんいかん。何をやっているんだ、と思い直し、信也が急いで立ち去ろうとした、そのときだった。
「下宮信也」
急に、背後から名前を呼ばれた。
「えっ……」
振り返るが、そこには膝を閉じてしゃがんだ着物の女性しかいない。
その女性がにこにこ微笑みながら、信也の方を見ている。
「どうしたんだい。きょとんとしちゃって」
「あ、あの、今、俺の名前を呼んだのって……」
「あたしあたし」
戸惑う信也の態度をよそに、缶ビールを片手に、彼女は実にフランクに話しかけてくる。どうして自分の名前を知っているのだろう。知り合いだっただろうかと信也は考えるが、思い出せない。
「え、えと……」
名前を訊ねてもいいものか。名前以外にも、気になることはたくさんあるのだが、とりあえずそれを訊こうと信也が口にしかけたとき、女性の方が先に口を動かしていた。
「下宮信也、『縁』、買っていかないかい?」
耳慣れぬ言葉に、信也は眉をひそめる。
「え、えん?」
「そう。縁だよ、縁」
女性は言いながら空中で指を動かす。信也向きに、『縁』と書いたようだった。
「え、縁を買う? 何言ってるんですか? それよりあなた、何者ですか……」
ようやく質問ができた。初対面かもしれない相手に「何者」は失礼だっただろうか。でもとにかく、この不思議な雰囲気を纏った女性の正体を、信也は知りたかった。
信也の問いかけに、女性はようやく気づいたのか、腕を組んで「ふむ」と頷いた。
「そうだね。ではまず名を名乗ろう。あたしはアガミ、ハツノセアガミ。親しみをこめてアガミンと呼んでくれたまえ」
「……アガミさん」
信也がそう言うと、途端に彼女は顔をしかめる。
「つれないねぇ。なぜそう距離を取りたがる。日本人の悪いくせだよ、しもっち」
「しもっち!?」
あだ名で呼ばれたのはいつぶりだろうか。信也の胸の奥で、何かざわめくものがあったが、今は目の前の女性のことの方が気になった。
日本人の悪いくせと言うが、礼節を重んじるのも大事だろう。
というか、そっちだって──。
「あたしだって、日本人じゃあないか。そう思ったかい?」
にたりと笑って言うアガミに、信也はドキッとした。まるでばっちり心を読まれているようだった。そんなにわかりやすい顔をしていただろうか。
「アガミさんは、日本人じゃないんですか?」
信也はそう訊ね返した。
金髪ではあるけれど、アガミの顔だちは日本人的で、日本語もものすごく流暢である。十中八九、信也はアガミを日本人だと思っていた。
だが、アガミが笑いながら発した返答は、予想もしない──できないものだった。
「あたしは神だよ。だから、そんな人種じゃあくくれないんだ」
「か、神?」
「そう。みんな大好き、縁結びの神様」
アガミは平然と、そんなとんでもない設定を語ってのけた。だが信也の脳内は大混乱だ。
神様だって? 縁結びの神様? だからこちらの名前を知って……。いやいや、そんなまさか。
信也は一度、深呼吸をすると、冷ややかな目でアガミを見る。
「なんで神様が、こんなところに座りこんでビール飲んでるんですか……」
「あたしの神社はね、とてもお客が少ないんだ。だから、こうして神自ら出向いてやっているわけだよ。人間に見える姿でね」
「はぁ。で、コンビニで買い食い、と」
「やー、お賽銭でいただく焼き鳥とビールは最高だよ」
そう言って、アガミは若干赤らんだ顔を幸せそうに綻ばせる。信也はますます視線を冷ややかにした。
まぁ、思考が混濁して妄言を吐いているただの酔っ払いだろうな。
そう信也が思っていると、アガミはむーっと頬を膨らませた。
「なんだいなんだい、呆れたような顔して。仕方がないだろう? こうしてコンビニの前にいるとね、中でホットスナックなんか買った人が袋を開けて食べながら帰っていくのをよく目撃するのだよ。そうすると、ついつい自分も食べたくなってしまうのが自然の摂理だよ」
「じゃあ、なんでコンビニの前に居座ってるんですか」
そもそもの疑問が生まれてしまった。
「それはあれだよ。あたしはみんなにお手軽気分で縁を買ってもらいたくてね。そこで、手軽さを売りにしているコンビニさんと、業務提携しているというわけだ」
「業務提携って、ただアガミさんが営業中のコンビニに便乗してるだけに見えるんですけど」
「そこはまぁまぁ。とにかく、ここなら人もくるし、たくさんの縁を結ぼうと頑張っているわけなのだよ」
縁結びの神様としてね。そう言ってアガミはふっ、と笑みを漏らした。
──その笑いが、どこか自嘲めいたものに感じたのは、気のせいだろうか。
正体やここにいる理由は一応説明された。が、やはり胡散臭さは拭いきれない。こんなめちゃくちゃな神様がいてたまるか。酔っ払いじゃないなら、自分を神と称して売りにしている占い師か何かだろうか。縁を結ぶなどと言っているし、占い師ならしっくりくる。
「そこで、話が戻るわけだよ。下宮信也、縁、買っていかないかい?」
アガミからの信也の呼び名はフルネームに戻っていた。さっきの「しもっち」は気まぐれだったらしい。
「縁、ですか……」と信也は呟く。
「そうそう。誰かの名前を挙げてもらえたら、あたしがキミとその人との縁を結んであげようじゃあないか」
縁。人間関係。
それはあっけなく、信じられないものだ。
信也が黙っていると、「ふふっ、どうするかい?」と、アガミが微笑みを湛えながら訊いてくる。
「いや、いらないですよ」
「ほぅ、どうしてだい?」
「どうしても何も意味がわかりませんし。だいたい買うって、いくらで買えるんですか?」
その話がでたらめかどうかは別にして、値段を聞いていないのに「買う!」などと簡単に言えるわけがない。
縁。それはいったいいくらで買えるのだろう。その相場は単純に気になる。
アガミは首を横に振った。
「お金じゃあないよ。円で縁は買えない」
『円』、『縁』と指で空中に書きなぞる。
「神社に賽銭を奉納して祈りを捧げるのとはわけが違うからね」
「はぁ。でも、お金じゃないんだったら……」
「ほしい縁があるなら、代わりに別の縁を売ってもらう。誰かと結ばれたいのなら、他の誰かとの関係を切らせてもらう。ウチはそういうシステムになっているのさ」
縁には縁を。それならば祈るのと違い、アガミは確実に縁を結んでくれると言っている。
他の誰かとの縁か……と信也は考える。
「その売るのって、男との縁でもいいんですか?」
「おやおや、キミは盛大に勘違いをしているよ。あたしの言う縁が、恋人関係のことだと思ったかい? 男も女も関係ない。例えば友達同士、上司と部下、先生と生徒、どんな繋がりであってもそれは縁だ。あたしの師匠なんかはね、人間関係のみならず、この世のいっさいの縁を統率なさっているよ」
「はぁ……。師匠なんているんですか?」
「いるさ。禁厭の祖神なんて呼ばれている、とても怖い人だけど」
そう言いつつ、辺りを見回すアガミ。周囲にその師匠がいないか確認しているようだ。彼女の妄想と考えるにしては、やけにリアルな警戒具合だった。
やがて、アガミが信也に向き直る。
「でも今の質問の仕方で、下宮信也が女の子との縁を望んでいるとわかったよ。少年、絶賛片想い中かい?」
「別に、そんなんじゃないですよ」
縁結びといえば男女のイメージがあったため、質問してしまっただけだ。だが、
「ふーん。へー。ほー。まぁいいさ。じゃあ、さっそく名前を言ってみたまえ」
アガミがにやにやしながら言ってくる。なぜだ、気づけば縁を買う流れになっている。
「いや、だから、縁なんていらないですって」
「ほぅ。でも、ほしい縁の一つくらいあるだろう?」
「ないですね」
きっぱりと言い切る信也に、アガミは目を丸くする。
「誰でもいいんだよ? 好きなアイドルでも、憧れる大人でも」
「アイドル? 面識がない人でもいいってことですか? そんなのできるんですか?」
「できるよ。名前が挙げられれば、あたしは必ずその縁を結ぶ。そういうルールだからね」
ルール。そんなものが存在するのか、と信也は思う。縁を結ぶなどという突飛な話の中で、その言葉は妙なちぐはぐ感を持っていた。
「さぁさぁ、言ってみなよ」とアガミが急かしてくる。
決して縁がほしいわけではない。ただ、本当に有名人と知り合えるなら面白いではないかと思った。
この酔っ払いに期待などしていない。どうせできるはずないと思っている。でも、ここまで話を聞いたのだから、試してみるのも悪くない。
「じゃあ、梅林大樹さんとの縁を……」
信也は縁を買う流れに乗ってみた。挙げたのは、憧れのプロゲーマーの名前だ。
「ふむ、キミはいつから男が好きになったんだい? まぁいいや、じゃあ次に売る方の縁の相手を」
「勘違いしないでください。梅林さんと恋愛関係になろうなんて思ってませんからね、決して」
念を押して言いながら、信也は誰との縁を売るか考える。
しかし、仮にこの神様が本物だとして、縁を売ったあと、その人との関係はどうなるのだろう。
そう信也が思案する間、よっ、という掛け声と共に、アガミが立ち上がった。