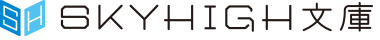カラフル ノート 久我デザイン事務所の春嵐 立ち読み
「違うんだっ!」
叫び声を上げながら、誠一郎は目を見開いた。
荒い息をつく彼の視界に、見慣れた天井が入ってくる。紛れもない、自分の部屋だ。
カーテンの隙間からは朝日が差しこみ、誠一郎の顔を照らしている。その光が夢の中のスポットライトを連想させ、誠一郎は思わず顔をしかめた。
また、あの夢だ。
誠一郎はベッドから体を起こし、気分を落ち着かせるように深いため息をついた。
まだ春先だというのに、体中がじっとりと汗で濡れている。汗で体に張り付いたTシャツが、少し気持ち悪い。
「……ったく、情けねえな」
片手で顔面を押さえ、呻くように声を漏らした。
あの事件から、もう二年以上が経つ。それでもいまだにこんな夢を見るのは、自分がまだ完全には立ち直れていない証拠だ。
一昨年の事件が、今も自分の奥底に深く根付いている。
そう思うと気が滅入ると同時に、誠一郎は自分のことがどうしようもないほど不甲斐なく感じられた。
「ああ、胸糞わりいな、ちくしょう……」
やり場のない感情から目を逸らすように、枕元に置いたスマホを手に取って、時間を確認する。表示されていた時刻は、午前七時だ。
昨夜は午前一時頃まで仕事をしていたから、睡眠時間は六時間ほどか。誠一郎の感覚で言えば、まだまだ寝足りない。
けれど、最悪の目覚めの所為か、どうにも目が冴えてしまっている。何より、あんな悪夢を見た後では、二度寝しようという気にもなれなかった。
「シャワーでも浴びるか」
少しでも気分を変えるため、誠一郎は湿ったTシャツを脱ぎ捨てて、浴室へ向かった。
途中、洗面台の鏡に映った自分の顔を見る。ミディアムに近い黒髪に縁取られた、慣れ親しんだ顔だ。しかし、普段なら可もなく不可もない細面の顔が、今は目の下のクマで見られたものではなくなっていた。
これはいけないと急いで浴室に入り、目の下をマッサージしながら蛇口をひねる。
熱めのお湯で不快な汗を洗い流すと、ざらついていた心中も幾分マシになってきた。汗と共に、悪夢が自分の中から流れ落ちていくような心地だ。血流が良くなったためか、クマも目立たなくなった。
シャワーを浴びてひとまずサッパリした誠一郎は、続いて朝食の準備に取りかかった。
トースターで食パンを焼きながらコーヒーを淹れ、冷蔵庫から苺ジャムとついでに食べかけの板チョコを取り出す。焼けたパンを皿に載せてテーブルに並べれば、朝食の完成だ。
「いただきます」
テレビで朝の報道番組を見ながら、朝食を食べる。
今日は十時半から次の仕事の打ち合わせだが、予想外に早く起きてしまったため、時間には余裕があった。原因が悪夢というのは考えものだが、早起きも悪いことばかりではない。食器を片付けた後は、部屋の掃除をして時間を有効活用する。
そして、時計がちょうど十時を回った頃のことだった。
─―ピンポーン!
「ん?」
突然のチャイムの音に、誠一郎は玄関へ目を向けながら、掃除機のスイッチを切った。
今一度、時計を確認すれば、間違いなくまだ十時だ。約束の時間まで、まだ三十分くらいある。
もしかして、アポイントメントの相手がもうやってきたのだろうか。
掃除機を壁に立てかけながら、誠一郎は首を捻った。
「いや、でもあの人が三十分前にくるなんてありえんよな。あの人、いつも計ったみたいに約束の時間五分前だし」
今日会う相手の顔を思い浮かべて、誠一郎は即座にその可能性を否定した。
では、外にいるのは新聞の勧誘だろうか。
誠一郎が首を傾げていると、チャイムがもう一回鳴らされた。
「はいはい、ちょっと待ってくださいよっと」
気だるげな顔で玄関まで出ていき、鍵を開ける。
今度、勧誘お断りのシールでも作って、玄関先に貼っておこうか。そんなことを考えながら、誠一郎は玄関の扉を開け放った。
「……は?」
扉の向こうにいた予想外の来客に、誠一郎は間抜けな声を上げながら目を瞬かせた。
玄関先に立っていたのは、一冊の本を大事そうに抱えた、高校生と思われる少女だった。
セミロングの艶やかな黒髪に健康的な白い肌。それらが陽光に照らされて輝いている。
その身を包んでいるのは、おそらく学校の制服なのだろう。紺のブレザーとチェックのスカートだ。落ち着いた色合いの制服だが、少女から発せられる華やかな雰囲気の所為か、妙に可愛らしく見えた。
ただ、それにも増して何より印象的なのは、彼女の大きな瞳だ。その黒曜石のような瞳は強い意志を湛え、どこか勝ち気な雰囲気を漂わせていた。
クラスにいたら、きっとスクールカーストのトップに違いない。常に人の輪の中心で、太陽のように明るく笑っている人種だろう。
それが、誠一郎の少女に対する第一印象だった。
だが、今はのん気に目の前の少女を観察している場合ではない。
「ええと、どちら様?」
愛想笑いを浮かべ、誠一郎が戸惑いながら少女に尋ねた。相手が見ず知らずの、しかも明らかに未成年とあって、その口調は少々ぎこちない。
しかし、それを聞いた少女は、なぜか小さく唇を噛んだ。その仕草には落胆の色が見えたが、誠一郎もそこに気を回してあげられるほど落ち着いてはいなかった。
御年二十四歳の自営業かつ一人っ子である誠一郎には、男女問わず学生の知り合いなどいない。
この子、訪ねる部屋を間違えたのではないか。
誠一郎は少女が自分の家のチャイムを押した理由を、そのように推測した。
ただ、それにしては少女の様子がおかしい。彼女は誠一郎の質問に答えることなく、ただ彼の顔を見つめているのだ。
その姿はあまりに真剣で、誠一郎は思わずたじろいでしまった。
「あの、君……」
「ねえ」
誠一郎が再び声をかけると、その言葉を遮るように少女が口を開いた。
外見と同じく、凛としていて澄み切った綺麗な声である。
「これをかいたの、あなた?」
そう言って、少女が大事そうに抱えていた本を、誠一郎の眼前に差し出した。
本のタイトルは『空を駆ける』。
走り高跳びの選手である女子高生が主人公の、六年ほど前に人気を博したベストセラー青春小説だ。加えて、誠一郎にとっても、とある理由で思い出深い本である。
だが、そのカバーを目にした誠一郎は、微かに眉をひそめた。
「いや、違うよ。俺は藤松敦史じゃない。そもそも小説を書いたことさえないし」
ややぶっきらぼうな口調で答えながら、誠一郎は首を横に振った。
藤松敦史というのは、『空を駆ける』の著者だ。誠一郎にとっては知らぬ相手ではないが、本人ではない。
故に否定の意を伝えたわけであるが、どういうわけか少女は誠一郎以上に不機嫌そうな顔となり、「は? 藤松敦史? 何言ってんの?」と宣った。
「この小説を誰が書いたかなんて、どうでもいいの。私、そもそも中身なんか読んでないし、興味もないし」
「いや、さすがにそれは言い過ぎでは……」
急に機嫌が悪くなった少女をなだめようと、誠一郎がしどろもどろになりながら声をかけた。
正直なところ、この少女は何が気に入らないのか、誠一郎にはさっぱりわからない。正に未知との遭遇といった心地だ。
あとついでに言えば、今の少女の台詞は、著者本人には絶対に聞かせられない。こんなことを真正面から言われたら、批評に慣れている作家でも、数日間は立ち直れなくなるだろう。この本の著者とは顔を合わせたことがある所為か、誠一郎は余計に不憫に思えた。
そんな誠一郎の心情などお構いなしに、少女は手に持った本を誠一郎の鼻先へと突きつけてきた。
「私が聞いているのは、この表紙の絵を描いた久我誠一郎はあなたかってこと!」
本に視界を塞がれたまま、少女の言葉を聞く。口調から考えるに、察しの悪い誠一郎に苛立っている様子だ。
ここまできて、誠一郎はようやく自分の勘違い、というか字の間違いに気が付いた。
ただ、この勘違いの責任を誠一郎に求めるのは、いささか無理があるだろう。普通、小説の単行本を見せられて「これをかいたのは」と聞かれたら、ほぼすべての人は『書いた』の字を当てはめるはずだ。
むしろ反省すべきは、紛らわしい言い方をした少女の方では、と思う誠一郎だった。
「で、どうなの?」
誠一郎の考えに頓着せず、少女は尋問でもするように詰め寄ってきた。
第一印象は勝ち気というイメージだったが、上方修正する。
この子は怖いもの知らずと言えるほど、気が強い。そして、色々と歯に衣着せぬというか、容赦がない。
ただ、今はそんなことはどうでもいい。問題は、少女が詰め寄ってきたという点だ。
当人は意識していないようだが、この距離はあらゆる意味で非常にまずい。目と鼻の先に、眉間にしわを寄せた少女の顔がある。その上、距離が近くなったことで、ほのかに甘い香りが誠一郎の鼻孔をくすぐっていた。今この場面を誰かに見られたら、修羅場と勘違いされるか、場合によっては警察に通報されてしまうだろう。
この危機的状況を乗り切る方法は、現状でただ一つだけしかない。誠一郎は若干のけぞり気味になりながら、少女の目を見て何度も頷いた。
「あ、ああ。久我誠一郎は俺だ。その装画も俺が描いた」
そう。誠一郎にとって『空を駆ける』が思い出深い本だった理由は、誠一郎がこの本の装画を担当していたからだ。それも、生まれて初めて装画した本である。
「それで、その絵を描いたのが俺だったら、一体何だっていうんだ?」
少女との距離感に余裕をなくした誠一郎が、早口で問いかけ返す。
すると彼女は誠一郎を見つめたまま、何か言うこともなくそろそろと身を引いた。気が付けば、先程までの苛立たしげな雰囲気も消えている。
ただ、誠一郎を見つめる少女の目には、いまだ強い意志の光が宿っていた。切実な事情がある人間特有の、不退転の覚悟というものに見える。
真っ直ぐな目で見つめられることに居心地の悪さを覚えた誠一郎は、軽く視線を泳がせた。
それでも少女は無言で、しかしどこか思いつめた面持ちのまま、誠一郎を見つめ続ける。
この奇妙なにらめっこで、先に根を上げたのは、やはり誠一郎だった。
「あ〜、それが聞きたかっただけなら、そろそろ……」
帰ってくれ。誠一郎がそう口にしようとした、その時だ。
突然、少女が「お願い!」と口を開いた。
その声の大きさに、誠一郎は目を丸く見開いて若干たじろぐ。
しかし少女は気にすることなく、再び誠一郎に向かって一歩踏み出し、そして……。
「お願い、私をあなたの弟子にして! 私、あなたに装画の技術を教えてもらいたいの!」
真剣な口調でそう言って、誠一郎の左手を両手で強く握り締めたのだった。
時間は少し流れ、まるで漫画のような二人の出会いから、ちょうど二十分後。
「……ふーん。葛城礼奈さん……ねえ」
「うん。可愛い名前でしょ。ちなみに花も恥じらう十七歳。この春から高校三年生!」
テーブルを挟んで向かい合うように座った礼奈が、学生証を片手に華やかな笑顔で頷く。先程までの苛ついた態度が一転、とても機嫌が良い様子だ。
なお、学生証を見る限り、彼女はさいたま市にある私立の女子高に通っているらしい。ということは、住まいもさいたま市内だろうか。
誠一郎がつらつらと考えていると、礼奈はさらに言葉を継いだ。
「誠一郎は私の師匠だから、特別に『レナ』って呼んでいいよ」
「さいですか。それは光栄なこって」
得意げに胸を張る礼奈に、誠一郎が投げやりな言葉を返した。
喜色満面の礼奈とは対照的に、誠一郎は渋い顔だ。
「ちなみに、ご両親はこのことについて何と言っていらっしゃるので?」
「あー、好きなようにしろって言ってる」
「それは許可していると言えるのか?」
「好きにしろって言っているんだから、問題ないでしょう。あ、もしかして挨拶とか考えているなら、別にいらないよ。気にしなくていいから」
無邪気に笑う礼奈を、誠一郎は疑い混じりの半眼で見つめた。
それも無理からぬことだ。なぜならこの状況に至るまでに、誠一郎にとっては寿命が縮むほど壮絶な一悶着があったのだから。
それは玄関先でのことだ。「弟子にして!」と手を握ってきた礼奈に対して、誠一郎は即答でこう返した。
「いや、無理だから」
取り付く島もないほどきっぱりとした、拒否の答えである。
相手は、今さっき初めて会ったばかりの少女だ。そんなよく知りもしない相手に対して、「じゃあ今日から弟子にしてあげよう!」なんて言えるわけがない。もしここで了承するようなら、そいつには間違いなく裏がある。
つまりこの対応は、ごく自然なものであり、当然なものである。少なくとも、誠一郎にとってはそうだ。
しかし、そんな理屈がただの建前でしかないことも、誠一郎自身が一番よくわかっていた。
今の自分には、誰かに装画を教える資格はない。それが誠一郎の本音だ。
つまるところ、相手が誰であるかは関係ない。たとえ気心の知れた相手であっても、誠一郎は同じ回答をしただろう。そう答えざるを得ない理由が、誠一郎にはあるから。
一方、誠一郎の答えを聞いた礼奈の表情は、僅かだが悲痛そうに歪んだ。
ただ、礼奈も今の答えだけでは納得できなかったようだ。
その証拠に、彼女は誠一郎の手をより一層強く握り締めた。女子高生とは思えないその握力の強さに、誠一郎が顔をしかめる。
「お願い! 私、どうしても装画の仕事ができるようになりたいの!」
「い、いや、だから俺は、弟子なんて取れないわけで……」
痛みに耐えながら、誠一郎が再び否を突きつける。
すると礼奈は、見ている者を虜にするような可愛らしい笑顔を浮かべた。一瞬、納得したのかと思われたが─―直後、彼女は渾身の力で誠一郎の手を握り締めた。
「お・ね・が・い〜!!」
「ちょっ! 痛い! マジで痛いって!!」
堪らず誠一郎は、本気の悲鳴を上げた。