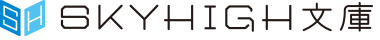花屋の倅と寺息子 立ち読み
俺は騒がしいのが苦手だ。特に飲み屋とか、酔っ払い共が五月蝿いところは近づきたくない。だから飲み会など無縁だと思っていた。
それが今、どうしてこんなことになっているのだろうか。
「─―今日は楽しんで行きましょう! 乾杯!」
「かんぱ〜い!」
乾杯の音頭と同時に楽しそうな声が耳に入る。
俺は友人たちに挟まれており、目の前には初対面の女が三人。どうやらこれが俗に言う「合同コンパ」らしい。
「悟も乾杯!」
俺は幹事の種岡亮太を睨みながら無言で烏龍茶が入ったコップを種岡のコップにぶつけた。しっかりとスタイリングした茶髪の種岡はいかにも大学生らしく、こういった遊びの仕切りも慣れているようだった。一方の俺は、大学に入学して二ヶ月が経とうとしているが、学校や新しい街にはだいぶ慣れたといっても、こういった遊びとは今まで縁がなく、知り合いと呼べる者だってまだ彼と、俺の左隣に座る統吾しかいない。
そんな数少ない知り合いである種岡が「一緒に飯食べに行こう」と言うから来てみれば、この合コンに参加させられたという訳だ。どうせ、俺に正直に「合コンへ行こう」と言っても来るはずがないと思ったのだろう。確かにそうだが、一緒に誘われた統吾にはちゃんと合コンだと伝えていたというのには、何とも言えない苛立ちが込み上げてくる。
今日の飲み会の名目は“失恋パーティー”ということらしい。種岡の友達の友達─俺から見たらただの他人だが、その人物が彼氏と別れたからその心の傷を癒やしてあげるために集まったと聞いた。その癒やす方法が新たな出会いを求めての合コンかと思うとため息が出るが、今更文句を言っても仕方ない。
「─―ほら、次はお前だぞ」
種岡が俺の肩を叩く。斜め前の女が「亮太君マジ面白〜い」とはしゃいでいるので自己紹介でもしていたようだ。まったくもって聞いていなかったが、聞いていたところで俺にメリットがあるとは思えない。
俺は表情を変えずに名乗った。
「柄沢悟です」
「それだけ?」
「……よろしくお願いします」
あまりに簡潔な自己紹介に、種岡の「終わりかよ!」というツッコミが入ったが俺は無視した。俺は自己紹介が好きではない。「悟」と書いて「サトリ」と読むのだが、みんな「サトル」としか読まない。一般的にはそうとしか読まないからしょうがないが、たまに親父を怨みそうになる。だから、名前について深く突っ込まれる前に終わらせたかったのだ。そんな俺の名前を間違えないように統吾は「さとりん」と呼ぶのだが、正直やめてほしい。たとえ、そのおかげで「サトリ」と読まれやすくなったとしてもだ。
その統吾の自己紹介は、無愛想な俺とは、真逆のものだった。
「高爪統吾でーす。絹子川学院大学の文学部で、特技は花のアレンジメント、趣味はギターを弾くことでーす」
ここまでは一般的だろう。ただ、そこから足の大きさからスリーサイズまでベラベラと喋り続けるのはなんなのだ。その様子に女たちが引いているのを感じて、俺は彼の橙色の頭を軽く叩いた。そもそもなんでお前は自分のスリーサイズなんて知っているのだ。
「いって〜。何するんだよ、さとりん」
「誰がさとりんだ」
俺はもう一度その頭を叩く。初対面の人間の前でそのあだ名で呼ばれると、聞いた奴らみんながそう呼び出す。それだけはどうしても避けたい。
そう思った矢先だ。
「それじゃ、統吾君もさとりん君も亮太と大学一緒なんだね」
小柄でショートヘアの女が言ってきた。言わんこっちゃない、もう広がりやがった。
「柄沢でいいで」
「ほら、あたしと美波と大学一緒だって」
すかさずフォローを入れるが、ショートヘア女が遮る。しかもこの女、話しかけておきながら俺の話を無視して、隣の髪の長い奴と話してやがる。
俺の怒りのボルテージが上がったのに気づいたのか、種岡が「まあまあ」と俺をなだめた。
ショートヘア女に美波と呼ばれた女は「そうだね……」と返事をするが、目は落としたままだ。向かいに座っている髪の長い彼女は、たとえ俯いていても視界に入った。
染めたことがなさそうな黒くて長い髪の毛先には、人工的に作られたようなウエーブがかかっている。上の名前は遠山というらしいが、同じ大学とはいえ学部が違うからか俺は彼女たちのことを知らなかった。そもそも、女は髪形が似ている奴も多いし、みんな同じに見える……と言ったら統吾や種岡に怒られるだろうか。
「それじゃ、あすなと美波は三人といつでも会えるじゃん。いいな〜」
遠山の隣のもう一人の女は、彼女の腕を抱きながら、なぜか俺を見る。舌足らずな喋り方に苛つく。そしてどうして俺を見るのだ。扱いに困った俺は無意識に頭を掻いた。
それが遠山美波との最初の出会い。
そして、俺と統吾がこれから巻き込まれる事件の発端でもあった。
それから二時間ほどして苦痛でしかない時間が終わった。種岡は他の二人と二次会に行くようだが、明日も講義があるし、何よりさっさと帰りたかった俺はその誘いを断った。
どうやら統吾と遠山もこのまま帰宅するらしく、三人で彼らを見送った。
彼らと別れた途端、じめっとした湿気を感じ、空を見上げる。大粒の雫が空から落ちたのはそれからすぐ後のことだ。瞬く間に雨が降り注ぎ、あっという間にコンクリートを濡らす。
「マジかよ。傘持ってねえや」
統吾が地面を見ながら呟く。この突発的な大雨はにわか雨だろうか。突然の雨に、隣に立つ遠山も困り果てた顔で空を見つめる。
「……送るか?」
俺は親から借りた車のキーを指で回した。初対面とはいえ、俺だけさっさと帰るのはどうも気が引けてしまう。
しかし、遠山は困惑しているようだった。今日会ったばかりの男の車に乗るのだ。警戒しているのだろう、無理もない。
そんな警戒心を崩すように、横から統吾が明るい口調で言った。
「だいじょーぶ。俺たちは美波ちゃんに手を出すようなことなんてしないよ!」
統吾は乗せる気がなかったのだが、ひとまず彼に同意した。勿論俺は手を出す気はないし、統吾だってこんな橙色のちゃらけた髪をしているが、そんなことをする度胸はないと知っている。
変わらず困惑顔のままの遠山だったが、どんどん強くなる雨足に「……お願いします」と丁寧に頭を下げた。
遠山を後部座席に、統吾を助手席に乗せ、俺は車を走らせた。
雨音は車内にいても耳障りなほど五月蝿く、雨粒はワイパーを最大速度にしても俺の視界を奪う。これは油断していると事故になる。俺は気を引きしめた。
車内では雨音に交じり、統吾の一方的なトークが繰り広げられていた。遠山はうろたえながらも懸命に相槌を打つが、完全に統吾のマシンガントークに押されている。なんだか申し訳ない気持ちになった。
もうすぐ遠山の家に着こうという頃、急に統吾が言い出した。
「それにしてもさ、美波ちゃんの友達ってみんな優しいよね」
いきなりの統吾の発言に遠山は戸惑っている。そんな彼女の様子に構わず、彼は続ける。
「今日は、君を元気づけるための飲み会だったんだろ?」
その言葉に息を呑んだ遠山は、小さく頷いた。バックミラーに映る彼女の表情は暗くてよく見えなかった。
彼女の家の前で俺は車を停める。
「元気出た?」
「……うん。ありがとう」
遠山は一礼して、車を降りる。統吾は雨の中小走りで去っていく彼女に手を振り、俺はそのやり取りをただ眺めていた。
「……お前、よくわかったな」
「んー? そりゃ、見ていたらね」
もう姿が見えない彼女に統吾は痛ましげな視線を送る。統吾は人の気持ちにとても敏感だ。なので落ち込んでいた彼女が気になっていたのだろう。
そんなふうに人の気持ちがわかる統吾を少し敬いながら、俺は気を引きしめ直し、アクセルを再び踏んだ。
「可愛いかったなー、美波ちゃん」
車の運転をしている俺の隣で、統吾は頭の後ろで手を組みながら呟いた。
「そうか?」
特に興味がなかったため、俺は適当に返事をした。しかし、受け流された統吾は不満なようだ。
「さとりんって本当にそういうの疎いよな」
別に俺だって「この人綺麗だな」と思う時はあるので、全く女に興味がない訳ではない。ただ、人を好きになったことがないので積極的にそういった感情が湧かないだけだ。そう言うと統吾は「ふーん」と相槌を打って視線を進行方向に戻した。
「なんで美波ちゃん別れたんだろうなー」
「そんなに気になるなら、お前が行けばいいだろ」
俺はすかさず統吾を茶化した。
「な、で、できないよそんなこと!」
暗くてよく見えないのが惜しいが、統吾の耳まで赤くなる様子が目に浮かんだ。本当にこいつをからかうのは弟を相手にしている時くらい面白い。俺は肩を揺らして笑った。
俺は恋愛に興味ないし、統吾は小心者。種岡はいい人止まりで三人とも現在恋人というのがいない。大学生なのに淋しい奴らと思われるかもしれないが、俺は十分にキャンパスライフを楽しんでいた。
もう少し統吾をいじめていたいところだが、残念ながら彼の家に到着したので、俺は車を停めた。
「それじゃ、ありがとう」
統吾は礼を言いながら車から出ようとドアハンドルに手をかける。
“奴”が出たのはその時だった。
統吾が「あれ?」と声をあげる。どういう訳かドアが開かない。がちゃがちゃと何度もドアを押そうとするが、微動だにしないのだ。ロックは解除しているはずである。不思議に思った俺も運転席のドアを開けようとした。しかし、こちらのドアもぴくりとも動かない。流石の俺も焦った。もしかしたら親の車を壊したのではないか。閉じ込められたということより、そっちのほうが心配だった。今思えば、意外と冷静だったのかもしれない。
雨は更に強まる。
大粒の雫が散弾銃のように窓を叩く。そして閃光が見えたと同時に雷鳴が響いた。かなり近くで雷が落ちたようだ。
「……さとりん」
統吾が俺の腕を掴んだ。手は汗でべっとりと滲んで、微かに震えていた。統吾は何かを俺に訴えていた。しかし、完全に怯えており、上手く声が出ないのか聞き取れない。
そんなに雷が怖かったのか? いや、違う。確かに統吾は小心者だが、雷なんかでこんなにも怯えないだろう。統吾がここまで挙動不審になるのは、あれだけだ。
再び雷が落ちる。
眩しく閃いた光は、バックミラーにあるモノを映し出した。それは後部座席で、俺たちをじっと見つめる見知らぬ男の姿だった。
「誰だ」
低い声で威嚇しても、男は答えなかった。年齢は俺たちと同じくらいか。目鼻立ちの良い優男だ。だが、男には表情がなく、下ろした前髪からは虚ろな眼差しが覗いている。
「誰だと聞いている」
もう一度問いただす。それでも男は俺たちを睨みつけるだけで、口は開かなかった。
この男が生身の人間ではないことは間違いない。幽霊と呼ばれる、魂だけの存在だろう。
生憎俺も統吾も第六感というのが冴えていた。小心者な統吾にとって、こいつのような害がありそうな魂は天敵だ。俺だって全く驚いていないと言えば嘘になる。しかし統吾が怖がって使い物にならない今、俺がこいつをどうにかしないといけない。だが、相手が何も喋らない以上、俺も打つ手がない。睨み合いがしばし続いた。
やがて彼が口をゆっくりと開いた。
「……て、がみ」
「手紙?」
男が発した言葉を確認するように反芻するが、男は俺を見つめたまま動かなかった。
その時、突如雨音に交じり、コンコンと窓を叩く音が聞こえた。